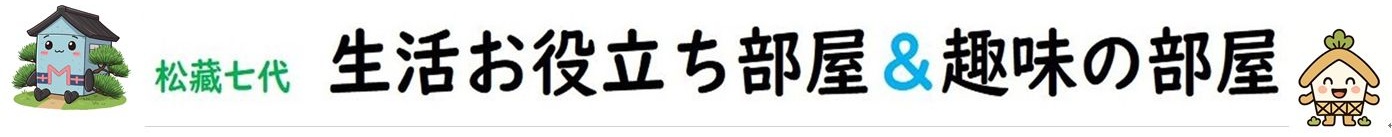心が洗われるような癒しの風景画|水彩画34作目 熊野那智大社 参道【世界遺産・紀伊山地の霊場と参詣道】
いつもブログ「Makuro7.com」をご覧いただき、誠にありがとうございます。
前回33作目から、水彩画を個別の記事としてじっくりご紹介する形に変更いたしました。今回はその第二弾として、水彩画34作目「熊野那智大社 参道」をご紹介します。
熊野那智大社は、言わずと知れたユネスコ世界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』の一部であり、熊野速玉大社、熊野本宮大社とともに熊野三山を構成する由緒正しき聖地です。
私がこの風景を描いた日はあいにくの雨模様でしたが、その悪天候こそが、霧が立ち込め、石畳が濡れてしっとりとした、なんとも言えない神秘的な景色を生み出してくれました。本作品は、雨と霧に包まれた幻想的な参道を通して、古道の持つ深い精神性と癒しの力をお届けしたいという想いを込めています。
【作品解説】雨と霧に包まれた世界遺産「熊野那智大社 参道」

雨上がりの霧が醸し出す「非日常」の情景
熊野那智大社の参道といえば、石段と、左右にそびえる杉の巨木が印象的です。しかし、この作品の主役は、雨上がりにかかった深い霧です。
遠景がぼやけ、色彩がわずかに抑えられることで、現実から切り離されたかのような非日常感が生まれています。この「霧のかかった景色」を描けたのは、まさに雨の日という偶然のおかげであり、水彩画の透明感と水の表現が最大限に活かされた仕上がりになったと感じています。
作品のポイント:世界遺産の「旗」が示す道
作品の左側には、朱色の社殿に続く参道を示すかのように旗が立っています。この旗には、「紀伊山地の霊場と参詣道」の文字がはっきりと描かれています。
紀伊山地の霊場と参詣道は、2004年7月7日にユネスコの世界遺産に登録されました。推薦当初は「紀伊山地の霊場と参詣道および周囲の文化的景観」という長い名称でしたが、現在の名称に落ち着いたとされています(web調べ)。
この旗を作品に入れることで、単なる風景画ではなく、1700年の歴史を持つ「信仰の道」を描いていることを明確にしたかったのです。霧でぼんやりとした風景の中に、この旗の文字だけが、参拝者を導く道標のように浮かび上がっている様子を表現しました。
絶景:参道の先には那智大社と日本三名瀑
参道を登りきった右奥には、朱塗りの熊野那智大社の社殿が立ち並びます。そして、そのさらに奥からは、日本の誇る大自然の造形美、那智の滝(那智の御瀧)が流れ落ちる壮大な景色が望めます。
那智の滝は、幅13m、高さ133mを誇り、毎秒約1トンの水が流れ落ちるその光景はまさに絶景であり、日本三名瀑の一つに数えられています。当日は残念ながら傘をさしての参拝となりましたが、その分、空気が澄み、滝の轟音がより荘厳に響き渡ったことを今でも鮮明に覚えています。
熊野那智大社の歴史と神々:「結びの宮」と八咫烏の神話
創建1700年。「滝の神様」から始まった歴史
熊野那智大社の歴史は古く、創建より約1700年とも言われています。元々、熊野の神々は、山の中腹にある現在の社殿ではなく、那智の滝本にお祀りされていました。その後、山の中腹に社殿を造営し、熊野の神々と滝の神様をお迎えしたことから、現在の熊野那智大社の形が始まったとされています。
古くからの信仰の場であり、深い精神性と日本の自然を同時に体感できる場所として、多くの参拝者が絶えません。463段の石段を登りきった先に現れる、朱塗りの美しい社殿の姿は、まさに心が洗われるような落ち着いた美しさを放っています。
主祭神・熊野夫須美大神と「結びの宮」の信仰
熊野那智大社の主祭神は、熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)です。この神様は、日本神話におけるイザナミノミコト(伊邪那美命)と同一の神様とされています。
イザナミノミコトは、イザナギノミコトとともに日本国土と多くの神々を生み出した神様であることから、熊野夫須美大神は「結びの神様」として信仰されています。このため、熊野那智大社は「結びの宮」として崇敬され、人との縁や諸々の願いを結んでくれるパワースポットとして、特に若い世代の参拝者からも人気を集めています。
神武天皇を導いた「お導きの神様」八咫烏
境内にある御縣彦社(みあがたひこしゃ)には、熊野の神様のお使いとされる、三本足の烏「八咫烏(やたがらす)」が祀られています。
八咫烏は、神武天皇が東征の際に熊野の山中で道に迷われたとき、道案内をしたという神話から、「お導きの神様」として崇められています。サッカー日本代表のシンボルマークとしても有名ですが、八咫烏(ヤタア)とは、古代の長さの単位で「大きなカラス」という意味合いがあるとも言われています。古来よりの神話とともに、参拝者をより良い方向へ導いてくれる存在として、ぜひ足を運びたい場所です。
【YouTubeで体感する熊野古道の魅力】大門坂から那智の滝へ
水彩画では一枚の静止画しかお見せできませんが、この地の魅力をより立体的に知るために、YouTube動画の内容を参考に、参拝ルートや見どころをさらに深く掘り下げてみましょう。
熊野古道の入り口「大門坂」の石畳
熊野那智大社へ続く道の中でも、特に有名なのが「大門坂」です。この坂は、数百年前にタイムスリップしたかのような熊野古道の空気感を今も色濃く残しています。
動画『【熊野古道】大門坂〜那智大社〜那智の滝に行ってきた!』では、大門坂の入り口から旅が始まります。石畳の両脇には、樹齢数百年(動画では200年と紹介)の巨大な杉がそびえ立ち、その景色の荘厳さに圧倒されます。
また、別の動画『熊野でやってはいけないこと』でも紹介されている通り、大門坂の入り口にある赤い橋は「振ヶ瀧(ふりがたき)」と呼ばれ、現世と霊界の境い目とも言われる神秘的な場所です。この坂の始まりには、樹齢約800年の夫婦杉も見え、古道に踏み入る前の期待感を高めてくれます。
大門坂は、1kmほどの石段が続き、その後にさらに本殿まで続く階段(表参道から467段)が現れるため、「覚悟が必要」とされる道のりですが、その苦労を乗り越えた先に待つ達成感と、社殿の美しさは格別です。
那智大社と並び立つ「青岸渡寺」
大門坂を登り切って熊野那智大社に到着すると、その隣には青岸渡寺(せいがんとじ)が並び立っています。ここは天台宗の仏教寺院です。
かつては神仏習合の時代、那智大社と一体のものでしたが、明治の神仏分離政策により、現在は独立した存在となっています。青岸渡寺は、日本最古の観音巡礼である西国三十三所の第一番札所とされており、ここから約1,000kmに及ぶ巡礼の旅が始まります。
動画『【熊野古道】大門坂〜那智大社〜那智の滝に行ってきた!』でも、青岸渡寺の境内にある四重の塔 の前からは、那智大社の朱塗りの社殿と、背後にそびえる那智の滝を一望できる、有名な絶景スポットが紹介されています。
願いを叶える「胎内くぐり」と延命長寿の水
那智大社の境内には、拝殿の横に大きな楠(くすのき)の御神木があります。この御神木は、平清盛の弟である平の重盛によって植えられたとされ、樹齢およそ850年を誇ります。
この楠の幹には大きな穴が空いており、これをくぐることで願いを叶えることができるとされる「胎内くぐり」が行われています。
また、那智の滝の滝壺からは、古来より不老不死の仙薬が沈められているという伝説があり、滝の御神水は延命長寿の水とされてきました。動画『【熊野古道】大門坂〜那智大社〜那智の滝に行ってきた!』でも、飛瀧神社でこの御神水をいただく様子が紹介されており、多くの旅人がその水を求めています。
日本三名瀑・那智の滝の迫力と別宮「飛瀧神社」の神秘
那智の滝:御神体そのものの飛瀧神社
那智の滝(那智御瀧)は、日本の滝の中でも特別な存在であり、それ自体が熊野那智大社の別宮「飛瀧神社(ひろうじんじゃ)」の御神体として祀られています。
神社として、滝の神様である大己貴神(おおなむちのかみ)を祀っており、那智大社の創建が滝本から始まったことからも、この場所が熊野の信仰の原点であることが分かります。
動画で確認できるように、飛瀧神社では拝所のエリア(有料)に入ると、滝壺のすぐそばまで近づくことができ、高さ133mから落ちる水が岩を叩きつける大迫力と、水しぶきを肌で感じることができます。
古くから、熊野詣での人々は、この巨大な滝を「命の源」と捉えていたとされています。それは、江戸時代以前の過酷な徒歩での巡礼路をたどり着いた先に現れる、自然の巨大な力に対する畏敬の念から生まれた信仰でしょう。
季節の彩りと7月の扇祭り
熊野那智大社は、四季折々の自然の美しさを感じさせてくれる場所です。特に、3月末から4月初めにかけての桜の季節は必見です。上品で優雅な姿を見せる枝垂桜が参拝者を迎え入れ、古き良き日本の情緒を感じることができます。
また、毎年7月14日に行われる「扇祭り(那智の火祭り)」は、この地の神々を祀る勇壮な祭りとして知られています。重さ数十キロにもなる大松明を担いで、石段を上り下りする姿は、動画『熊野でやってはいけないこと』でも「迫力を見せてくれるご神事」として紹介されており、一度は見てみたい日本の祭りの一つです。
水彩画を描くヒント:雨の日の風景が持つ幻想的な魅力
最後に、私自身の水彩画制作の視点から、今回の作品が持つ魅力について解説します。
風景画を描く上で、晴れた日の鮮やかな色彩は魅力的ですが、雨の日や霧の風景には、それを凌駕する幻想的な魅力が秘められています。
- 色の深みと潤い: 濡れた石畳や樹木は、反射光を抑え、色に深みと潤いを与えます。特に水彩画の技法を使うと、このしっとりとした質感や、空中の湿った空気感を表現しやすくなります。
- 輪郭のぼかし: 霧は、遠景の建物の輪郭を優しくぼかし、手前のモチーフとの間に自然な空気遠近感を生み出します。これこそが、風景に「癒し」と「奥行き」を与える最大の要素です。
- 光のハイライト: 曇天であっても、雲の切れ間や霧の隙間から差し込むわずかな光は、濡れた地面で強く反射し、作品にドラマチックなハイライト効果をもたらします。
作品34は、あいにくの雨を「幻想的な景色を描くための最高の演出」として捉え、水彩画ならではの表現を追求した一枚となりました。
まとめ:次回は「熊野古道」へ
今回の水彩画34作目「熊野那智大社 参道」を通して、日本の霊場の中でも特に神聖な雰囲気を持つこの地の魅力をお伝えできたなら幸いです。
熊野那智大社は、徒歩でしか体感できない大門坂の修行のような道もあれば、バスや車で山の中腹まで上がり、気軽に朱塗りの社殿や那智の滝の絶景を堪能できるルートもあります。その壮大な歴史と自然美、そして人々の願いを結ぶ神様、お導きの神様が待つこの地へ、ぜひ一度訪れてみてください。
【那智大社の場所】 熊野那智大社の詳しい場所は、以下のGoogleマップをご参照ください。
次回の水彩画作品の公開は、作品36「熊野古道」となります。大門坂を含む、より深く「道」に焦点を当てた作品にご期待ください。お楽しみに!
下記は前回アップした33作目 高野山の紅葉を描いた水彩画のリンクとなります。
🔗【高野山の紅葉】心癒される秋の風景を描く|水彩画33作目・奥之院の静寂に包まれて – 松藏七代 生活お役立ち部屋&趣味の部屋